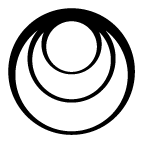「承太郎」
やっと開いた口から出たのは彼の名前だった。そのすぐあとに後悔する。呼んだのは私なのに、次にかける言葉が何も浮かんでいなかった。なんで、名前で呼んでしまったのか。
彼は私を一瞥すると、またもその水平線の向こうへと思いを馳せる。視線があった瞬間、微かに鼓動が止まったのは、そのエメラルドの瞳が濡れているように見えたからだろう。
小波が訪れる度に強まる潮の匂い。あの苦い煙草の匂いはどこにいってしまったのだろうか?
夕日も沈みかけ、半分もその姿を見せていない。オレンジに藍色が浸食しだしてきた。夜がきている。しかし星は未だ姿を現さない。
そんな時間に、高校生にもなって、風の強い浜辺で膝元まで海水に浸かっている人がいる。それがクラスメイトである空条承太郎だったと知り驚いたのは、何分前のことだったか。
「ねぇ、なんで私に話したの」
とても長い、旅の話であった。それは全く無関係だった私を巻き込むようなものではなく、ただそこにいたらたまたま独り言を聞いてしまったような、そんな落ちるだけの言葉達だった。結局は過去の話だということだ。
彼がどんな気持ちで口を開いたのかは分からない。話を聞いて欲しかったのだろうか、しかしそれは普段の彼からするとあまり考えられない。
ただ、場所が場所なこともあって、私にはもの悲しさと虚しさしか感じ取ることが出来なかった。
正直な所、どう受け止めればいいのかがわからなかったのだ。
そもそも空条承太郎とはそんなに深い関わりもなかった。クラスメイトという関係ではあるものの、大した会話もしたことがない。たまたま海が綺麗だったから、寄り道して帰ろうと足を運んだのが良くなかったのかもしれない。
心の底で、なんで私なんだろうと、聞かなければよかったと思っている、冷えた私に気付いていた。
何時もより小さく見える背中に、思わず目をこする。このまま放っておけば、波に溶けて死んでしまうのではないだろうか、そんなことすら考えた。
波は私の足元まで来ていた。スニーカー越しににじわりと冷たさが伝わる。繊維を超えて私に到達するのもそう遠くない。
彼の特製の制服もとうに濡れてしまっている。洗うのが大変だと、お母さんに怒られても知らないよ。なんて意味のない言葉を口にしてみる。思った以上に情けない自分の声に自分で驚いた。こんなでは波の音に消されて彼まで届かず落ちてしまったのではないだろうか。
案の定というか、彼からの返事は返ってこなかった。今度は振り向きもしなかった。ふと、私はここにいなくてもいいのではないかと、希望のような逃げ道が頭の中に沸いてきた。
さっきまでの話も全て、彼の独り言で、今彼はひとりになりたいに違いない。誰にだってそういう時はある。そう自分を納得させるも胸の奥の息苦しさは止まなかった。
「なんで私なの……」
理由が知りたい訳ではなかった。けれど、何故私がこんな思いをしなければならないのか、という怒りや恨みに似た何かがそろそろ溢れ出しそうだった。
どうせ答えてくれないのだし、もう帰ってしまおうか。
本格的に湿りだした靴に不快感を感じながら元来た方へ踵を返す。私はとんでもなく薄情者だ。
でも、それでも、何度考えても彼にかける言葉など見つからない。
地雷を踏むことを恐れているのか?いやそうではなく、もっと深い所へ沈んでしまいそうな気がして、ただそれが怖かった。
すぐに聞こえたパシャンという水音に思わず振り向いてしまった。ほぼ均一に聞こえていた波の音とは別のそれは、やはり波がたてたものではなかった。
「ちょ、ちょっと!」
音を立てながら、どんどんと深い所まで進んでいく男、空条承太郎は一体何を考えているのだろうか。彼の話を偶然にも聞いてしまった今、その思考回路がほんの少し分かってしまったことが何よりもつらかった。
その大きな背中が段々と沈んでいく。水音とともに小さくなっていく。
慌てて追いかけたのは、殆ど無意識だった。彼の体がすっかり見えなくなってしまうくらいには、冷たく深い海。濡れる靴もスカートも気にならなかった。
纏わり付く髪と衣服の重さに焦る。泳ぎは得意な方ではない。しかし彼はもっと重い自身をこの海に沈めようとしているのである。
残り僅かな夕日が照らす海の色は不気味で、このまま飲み込まれてしまうのではないかという恐怖を煽る。
ゴーグルも無い状態で、海の中は暗闇に等しかった。とうとう足も付かない深さまできて後戻りはできないと知る。目を開くと水が刺さる。息継ぎをしようとするも、予想外の波で鼻に水が入ってしまう。
ふと、小学校のころのプールの授業を思い出した。先生が投げたおはじきやビー玉を、もぐって探し、たくさん集めた人が優勝というあのゲーム。透明な水の中で、太陽の光に反射してきらきら光るそれを手にした時の高揚を忘れられない。泳ぐのがあまり好きではない私が一番好きだった時間。
しかし今いるのは海で、プールとは環境が全く違う。探し物も見つからない。
そうか、これが走馬灯っていうやつか。そう気付いた時には、酸素が底をつきかけていた。
最後に目を開いた時、歪んだ視界で何かが煌めいた。輪郭もないゆらゆらとした光。あまりに悲しいエメラルド。確かにそれをそこに見た。
咄嗟に腕を掴んでしまったのは、死にたくないと願ったからだ。死んでほしくないと願ったからでもある。
沈んでいくのを黙って見てはいられないけど、「沈む時は一緒だよ」とか言ってあげるつもりもない。そこは私なんかでは役不足だ。
腕をつたって感じた鼓動に少しだけほっとした。彼は必死で掴む私の腕を振りほどくことはしなかった。むしろ彼に引き寄せられたような、そんな気もした。
私はまだ生きている。私は生きたい。
潮風が生温かく、頬を撫でていく。
いつの間にか夜空に星が浮かんでいた。どれくらいの時間ここでこうしているのだろう。
濡れた体に、スカートに砂が張り付いてくるが、もう気にならなかった。ただ、明日の学校どうしようかと、それ以前に親になんて説明しようかなと、未だに乾かない制服を見下ろし考えていた。承太郎は、どうするのだろうか。
彼はまた海を眺めていた。トレードマークの帽子をその手に、星と海のその間を見つめている。けれどその足はしっかりと地面に立っていたし、振り向いた時のその瞳はとても真っすぐで綺麗だった。
しばらくして戻ってきた彼は私の前に立つと、濡れたポケットから何かを取り出した。
「見つけた」
「……何を」
「ウニ」
あんなに暗い水の中でよく見つけたなぁ、と素直に関心する。気の抜けるような会話、それに怒るような気力なはい。そんなことをする為に彼が海へ入ったのではないと分かっていた。息が出来ているという実感だけでもう他の事は何だってよかった。例えその姿がどんなにシュールだとしても。
「すごいね、結構立派じゃない。ライターで焼いてよ」
「全部湿気っちまった」
「そりゃそうか。残念。しかしなんでまたウニを……」
「お前が好きだと、言ってたじゃねェか。それを……思い出しただけだ」
「……ありがとう」
なんで知っているのだろうか。そんな話をする程、彼と仲良くなかったはずだ。私が覚えていないだけだろうか。そんな疑問も浮かんできたけれど、それよりも溢れ出したのは笑いだった。なんだ、彼も走馬灯を見るんだな、と。
そんな私を彼は静かに見下ろしていた。
「見つけたぜ」
彼はこの海で何を待っていたのだろう。もし、私が通りかからなかったらどうしていたのか。
そんなことを考えていたら、いつの間にか私まで泣いていた。
「そう、私も」
寝て起きて、濡れた瞳が乾いた頃には朝が来る。彼はここにいる。
さよならノーチラス号
(遠い昔に別名義で書いていた作品をサルベージ)
back