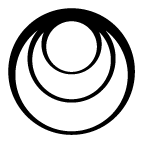※GX藤原優介の妹設定。名前変換はありません。
「やぁ、久しぶり」
「久しぶり、兄さん」
数ヶ月ぶりに見る顔に、頬が綻ぶ。その瞳に滲む翳りなど、再会に胸いっぱいの今、気付けるはずもなかった。
両親は私達がまだ幼い頃に交通事故で亡くなった。それ故に何年かは兄妹二人でアカデミアの寮で暮らしていたのだが、秀でた才能を持った兄は早々にオベリスクフォースとして引き抜かれ、今は任務として他の次元を巡っているらしい。
自分で言うのも何だが、事故のショックからか、ちょうどその頃から私達は「カードの精霊」というものが見えるようになった。兄にはオネスト、私には精霊術師ドリアードが、今も横で私達を見守ってくれている。彼等が、今も私達を繋ぎとめてくれているのには間違いがなかった。例え、「見えないモノ」と交信していると怯え蔑まれても気にもならない程に。
「誕生日祝いに、このカード達をあげる」
「えっ……本当に?ありがとう!兄さん」
「ラッピングも出来なくてごめんね」
「そんなの気にしないよ!」
そう言って差し出された数枚のカード。誕生日は数週間前にもう過ぎてしまったのだが、ちゃんと覚えていてくれたことに体温が上がる。ただただ、覚えてくれていたことが素直に嬉しかった。
「……クリアー・ワールド?」
始めて見たカード達に、興味を惹かれた。兄も使っているという。
次元戦争の中で、敵に対抗するためにデッキを変えたのだろう。何も珍しいことではない。オベリスクフォースになると、専用デッキも支給されるというし、もしかするとこれがそうなのかもしれない。ちらとオネストを見やると、どこか複雑そうな表情をしていた。
「お前ももし辛いことがあったらおいでね、いつでも迎えてあげるから」
「……うん」
「そのためにはもっと強くならないと」
兄さんが傍にいないのが、一番辛いのだと言えたらどんなにいいだろうか。また、明日には彼は私の前からいなくなるのだろう。
寂しい、悲しい、忘れられてしまうのでは?そう思ってしまうのは、兄の瞳が、私を見ていないからだ。その瞳に小さな私を捉えてはいても、そこに以前のような温かみが無い。感情が無い。それが寂しい。他に大切なものがあるのだろうか。黒い靄のような物が胸で渦を巻く。……行かないでほしい。
「どうした?」
「いや……何でも。気を付けて行って来てね」
しかし、現実はそう甘くない。親もいない私達には、今はアカデミアで生きる以外の選択肢はないのだ。ならば私も、なんとしてでも早くオベリスクフォースに選ばれるようにならなくてはいけない。今の成績ではまだ難しいかもしれないが、やるしかない。次に兄に会う時は、同じ制服を着ていたいと、そう強く思った。
「オネスト、兄さんをお願いね」
「…勿論です」
オネストが、ドリアードを見る。彼等も仲が良いから、何か思うところがあるのだろう。
それが、兄との最後の会話であった。
*
「君が新しくオベリスクフォースに入った子?……藤原さんだっけ」
「はい」
「……支給されたカードを、融合を使わないんだってね。確か……エレメントデッキだったっけ?儀式を使う……」
「オベリスクフォースになってから、もうそのデッキは使ってません」
私の返答に、彼はさして興味もなさそうに相槌を打つ。社交辞令として聞いただけと言わんばかりであった。
ついにオベリスクフォースになった私の初めての上司は、デニス・マックフィールドというよく掴めない男だった。まさか出会っていきなりマジックを披露されるなんて、思いもしない。年齢も近いということで名前も呼び捨てで構わないというし、かなり変わった人である。硬すぎたり、怒鳴るような理不尽な上司よりは何倍もマシではあるが、馴れ馴れしすぎるのもどうだろうか。
「もう一人、そろそろ来るはずなんだけど」
今日は、プロフェッサー直々の任務により、エクシーズ次元へと来ていた。デニスは以前からこの次元に馴染み情報を集めているらしく、与えられたレポートにはここでの衣食住についてや基本的なルールが事細かく書かれていて、いくら軽薄そうに見えても彼が優秀であるということが分かる。
はじめての他次元での生活に、胸を躍らせるようなことはない。確かに良い街ではあるが、何れここを私たちアカデミアが抑えるのだ。悠長に旅行気分でいれるはずもない。愛着が湧いてしまう前に、やるべきことをやらなくてはいけない。
高台から、賑やかでカラフルな街並を見下ろし目を細める。ハートランド、といったか。私達の次元とは、全く異なる風景だった。――彼は、この景色を見たのだろうか。
私のすぐ横で、ドリアードも私と同じようにぼうっと街を見下ろしていた。
しばらくして、その待ち人はやってきた。
「誰、この子」
突如次元を超えて現れたマントの少年は、私を見ると眉を潜めながらデニスに尋ねる。
「藤原さん、彼女もオベリスクフォースだよ。僕の部下」
「ふぅん、じゃあ僕の部下でもあるわけだ」
「彼はユーリ。名前くらいは知ってるでしょ」
「あっはい(知らない)」
「……にしても見ない顔だね」
「何でか分からないけど、プロフェッサーのお気に入りらしくてね、スピード出世したみたい……あっやべ」
ギロリ、と刺すような視線がこちらに流れてくるのが分かった。
その紫色の目が、少しだけ怖いと思った。同時に、誰かに似ているような気がした。そう、それはきっと最後に見た、あの瞳。
……?
私は何を考えているのだろうか。頭に靄がかかったように思い出せない。目をこすってみたら、なんだやっぱり全然似ていない。
「っていうか君すごく地味だよね、影が薄いというか、華が無いというか」
突然睨んできたかと思えば、今度はこの言い様である。デニス程フレンドリーで優しい上司ばかり望んでいる訳ではないが、最初から喧嘩腰の奴はもっと嫌である。
「……自分で言うのもなんですが、そういうところが、プロッフェッサーに気に入られたのかもしれません」
「(ユーリの顔が更に険しく)」
「あー、なるほどね?地味だから潜入操作に向いてる的なね?確かに僕みたいなのが彷徨いてたら目立つし、君には適任かもね。黒子のバスケかな?」
「ユーリ、その発言は色々とまずいよ。特に君が言うのは一番アウト」
まぁまぁと私たちを宥めるデニスに、未だ睨んでくるユーリさんをスルーして一歩下がる。いうてこっちが階級下だからまぁ、多少はね?中間管理職って大変ですね、一生臑を齧る立場でいようかな。
「気を取り直して、今回の作戦について話そうか」
「あの、これ先に融合次元で話し合ってた方が良かったんじゃ、こんなところ見られたら……」
「……ターゲットは彼女。……というか、この写真はうちの次元の生徒のものらしいけど、そっくりというか、同じ顔をしているらしい」
「スルーですか。やっぱり大丈夫なのこの上司」
あくまでもスルーを決め込むつもりらしい。
「しばらくまた僕は、……僕たちは二人でこの次元で生活してターゲットを見つけ出し、接触を図る」
「ははは、面白いね。一夜の過ちでも起こしちゃいなよ」
「ははは、この子にそんな気起きないよユーリ。でもおつまみ程度に食べちゃおうかなーなんて」
「セクハラでプロフェッサーに報告します」
最近、何故か物忘れが激しくなったため、こういった打ち合わせはこっそり録音しているのである。今この時点で私より上は存在しない。
冗談などと言って大袈裟なお世辞を述べるデニスをただじっと見つめると私が本気であると理解したのか、咳払いをしてから再び口を開いた。
「藤原さんはレディだし、僕よりも仲良くなれるんじゃないかな?」
「仲良く……?ああ、それはターゲットを見つけた後の話ですね」
「そう、まずは油断させないとね」
そういってデニスがこちらに向かってウィンクした。それをユーリがこちらにパスしてきたので、ダンクシュートの如く地面に叩き落とす。バスケネタ引きずるのやめようぜ。
「で、僕を呼んだ意味は?」
「彼女を紹介しようと思っただけだけど?」
「帰る」
デニスに腹パンを決めて、マントを翻した彼は少なからず怒っているようであった。そりゃ怒りますわ。
「……そういえば君、藤原っていったっけ」
「はい」
「兄妹は?」
「……?いませんけど」
「……ふーん、あの人の妹かと思ったけど、違うんだ。似てると思ったんだけどな」
誰かと勘違いしたのだろうか。首を傾げつつ、彼が消えるのを見送った。
面倒くさそうな上司だったね、と右隣を見て、目を見張る。
「何で泣いているの?ドリアード」
(主人公と合わなくて小姑のような態度をとるユーリ、無知故に上下関係も気にせず地味に喧嘩を売っていくスタイルの主人公に、板挟みで疲れるデニス。一見ほのぼのに見えてそれぞれの行く先には闇しか見えない傷の舐め合いのようなダークネスパーティー。ちなみにドラゴンパワーか何かでユーリだけは藤原を覚えているとかだといい)
【小ネタ】
「あの……ドリアードまで闇堕ちして帰ってきたんですけど……」
「良かったじゃん」
「ていうかペンデュラムモンスターって何なんだろう、ユーリ様知ってます?」
「スタンダードで最近生まれた召喚方法らしいよ」
「ふーん……何はともあれ良かったねドリアード。……しかし本当にタイムリー過ぎて怖いわ……」
???「ダンセル復活も現実味を帯びてきたね!」
「誰だいまの」
back