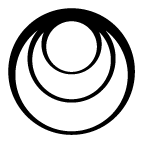夢というのはレム睡眠の時に見やすくなるというが、それならば私はいつもいつもレム睡眠なのだろうか。
ぱちりと眼前に広がった景色。淡い青色の空に張り付いたまま動かない雲と、その青色に少し絵の具を付け足し濃度を濃くしたような色の木々が、滲みながらその枝を日に日に伸ばしていく。高いところは薄く空に溶け込みはじめていて、この場所は遠近感がよく分からない。
地面には薄く水のようなものが果てのはてまで広がっていて、歩くたびに波紋を産む。歩いても歩いても続くのは同じような景色で、疲れることもないため距離感すらも分からない。勿論、靴が濡れることもない。……これら全て、夢の世界だからこそなのだろう。
一面ブルーの森。異様な程に青色の世界に、私は幾度もたどり着く。そして今日もまた同じ夢の中で、あの少年に会った。
「やっと起きた!」
遊矢は水面を跳ねながらこちらに駆け寄ると、そう言って私に笑いかけた。クリスマスカラーのその髪は、この世界で彼が異端であることを示しているかのように、浮いている。不思議な、少年。
「今日はやけに嬉しそうだね、遊矢」
「だって……あ」
そこまで喋って、彼は黙ってしまった。
彼はいつも、私がここにやってくることを「起きる」というけれど、私からしてみれば「寝た」はずなのである。遊矢曰く、彼も寝るのと同時にここにやってくるらしく、その時間がいつも私より早めであるらしい。それは、ただ単に私が夜更かししているということに他ならない、のだろうか?そもそも、遊矢が本当に私と同じような存在であるという証拠はない。もしかすると、彼は夢の中に生きる少年かもしれない。……最初はそう思っていたけれど、それはむしろ私なのかもしれないと、最近はそう思うようになっていた。
そう疑ってしまうのも仕方が無いことであった。この夢の中に来ると、途端に自分のことが分からなくなるのだ。今日はどこで、いつ寝たのか。それまで何をしていたのか、どんな物を食べたのか。そして、自分の名前すらも、霧がかかったように思い出せなくなるのだ。
それは、この世界ではきっと必要ないものだから、と最近は割り切ることにしている。その証拠に、必要最低限の知識と、この世界での記憶だけはなんとなく覚えている。この世界で必要なのは、この世界のものだけなのだろう。
それに夢が終われば、心配しなくてもまたいつもの日常に戻るのだ。多分、遊矢のいない日常に。覚えていないからなんとも言えないが、彼と会えない間は、起きている間は本来の私の世界に戻っているはず。たとえそうでないとしても、今こうして遊矢と話しているのだから、それで十分だった。だってこれは夢なのだから。
ならば、そんなに気にするところではない。そう思うことにしたのだが、目の前の少年にとっては違うようだ。
「……やっぱり名前が、知りたいな」
「名前?」
「そっちが俺の名前知ってるのに、俺は知らないのってなんかずるい」
「そんな事言われても、分からないんだもん」
「……そうだけど」
この世界での記憶はあるとはいえ、いつからこの夢を見出したのかはもう分からない。いつも変わることのない青色の世界では、時間の感覚も狂ってしまう。彼とであって、一ヶ月?一年?それ以上?それすらも、曖昧になっていた。
彼は度々私に名前をつけようとしたが、次に会うときには忘れていたり、また違う名前で呼んでいたりする。曰く、しっくりとこないから、ということらしい。
「そんなことより遊矢、今日はどうだったの?」
何もない世界で出来ることといえば、遊矢と話すことだけだ。しかし、私はあちらの世界の記憶を持っていないから、自然と私が彼の話を聞く形となる。
私の言葉に少しつまったものの、遊矢はまたぽつりぽつりと話しはじめた。
今日会ったこと、言われたこと、それらを私に教えてくれる。今は空っぽな私に、記憶を提供してくれるのである。
「俺、やっぱり無理かもしれない」
「無理……?」
「……また、理想のデュエルが出来なかった」
彼の世界には、世界的に人気なカードゲームがあるらしい。大体、彼が話すことはそのゲームについての話であった。それはどこか現実離れしていたが、嘘であると思ったことは一度もなかった。
「父さんみたいになろうとする程、上手く行かなくて、全く逆のデュエルになる……俺が本当にやりたいデュエルが出来ないんだ……!」
「遊矢……」
薄々感じてはいたが、最近の遊矢は何か悩んでいるような気がしたのは間違いではなかったらしい。その顔に笑顔を貼り付けてはいるけれど、どこかぎこちない。
「楽しくないの?」
「楽しくない、かな。もう、どうしたらいいのか……」
ぐるり、と空が微かに渦巻いたのを、私は見ていた。
「私、最近思ったんだけど」
「うん」
「この夢にもきっと、何か意味があるんだと思うな」
「難しいこと考えるなよ」
焦ったような遊矢の声が聞こえた。「ここは夢なのだから、楽しい話をしよう」そう言って彼はよく笑う。しかし、と私は続ける。ずっと、気になっていたのだ。何故、この世界は存在して、何故、私達がここにいるのか。
「夢を見る時って、大体疲れてる時じゃない?私か、遊矢。もしくはどっちも。きっと向こうの世界で疲れてるんだ」
つまり、彼は(または私は)日々しっかりと眠れていないのではないだろうか。人間にとって睡眠は大事なものである。今はそうでもないかもしれないけれど、この積み重ねが、彼の健康に被害を及ぼす可能性もないとはいえない。
そしてその理由は、彼の起きている時の世界にあるのだろう。
「あんまり、このままは良くないような気がする」
「あんたは、俺といたくないの?」
「そういう訳じゃないけど……」
「俺はここにいたくているんだ、それだけだよ」
ずるい言い方だと、思った。今のところ、この世界の記憶しかない私にとっては甘すぎる程の言葉。しかし。
「遊矢との話は楽しいよ。でもこれは夢だから、私が話を聞いてるだけじゃあ、遊矢は変われないんだと思う」
私は、結局遊矢の話を聞くことしかできなかった。遊矢視点の話を聞いているだけでは、彼にアドバイスすることも、上手く励ますこともできるはずがない。彼の望む答えも、分からない。ただ、頷くだけ。それは、彼の場合、知らず知らずにストレスや甘えをただ増幅させるだけであったのだ。お互い気付かなフリをしていたけれど、結果として、何も生まない、悲しいやりとり。
そして、私にできないことをできる人間は、彼のすぐ近くにいるはずなのである。彼が見えていないだけで、きっと。
「多分、遊矢自身が、向こうの世界の人達と、話したり、よく理解しようとしないと、駄目だ」
「……でも」
「遊矢、遊矢のいるところはあっちでしょ」
私と遊矢の住む世界は、違う。私に出来るのは、その背中をそっと押す事だけ。彼はただ黙って聞いていた。きっと、彼自身も分かっていたのだろう。もしかすると、最初から気付いていたのかもしれない。その日は、彼の夢が覚めるまで、ずっと隣にいた。
私の記憶が正しければ、遊矢と夢の中で会ったのはそれが最後である。次にこの世界に来た時、私は一人だった。
水の張った白い地面に寝転んで、目を閉じた。私が動かなければ、何の音もしない世界。私だけの世界。愛しい世界。相も変わらず、水の冷たさも、感触も、ありはしないけれど。
夢をみた。既に夢の中であるにも関わらず、おかしな話ではあるが、しかしそう表現することしか出来なかった。
子供達が笑っている。体格の良い少年が、優しい瞳で見つめている。ツインテールの女の子が笑いかける――彼等の視線の先に笑顔の遊矢がいた。色に溢れた世界。私が決して行くことのできない世界。
「遊矢、」
その時、私はようやく自分が遊矢に恋をしていたということに気が付いた。
確かに、私たちはこの世界にいた。不安定な二人の世界。否、遊矢の世界。そして、多分、もう必要のない世界。
ぽつり、と頬に何かが落ちてきた。何度も、何度も。段々とその間隔を短くしていった。はじめて、この青い世界に透明な雨が振った。強すぎず、弱すぎない勢いで、音も無くただただ降り続けた。淡い空や、青色の木々は、絵の具に水を溶かすように、上から色が落ちては地面を流れて行く。
「なんだ、やっぱり私が」
そうして気付いた時には、今まであったものはすべて溶けて、私が溺れる程の、一面の青い海となっていた。そう、この中に、きっと私の涙も混じっている。あとは私が、沈むだけ。それなのに、最後まで考えていたことは、ただ、彼に幸せになってほしいということだけだった。
end…?
海で溺れて死ぬ夢を見た。朧げにしか覚えていないが、怖いというよりも、哀しい夢だったような気がする。でも、それで良かった。縁起が良くない夢を見ることはたまにあるけれど、今日は何故か、むしろ清々しい気分で、目覚めは良好。まるで今日生まれたような気分だった。
朝の空気は澄んでいて、気持ちが良い。大きく深呼吸をすると、久しぶりに空気を吸ったような錯覚。これも全て、あの夢のせいなのだろう。私の名を呼ぶ、母の声がした。
リビングに行くと、甘い香りが辺りに漂っていた。お気に入りの赤いマグカップに入ったポタージュと、蜂蜜により黄金色に焼けたトーストが、私を待ち構えていた。食欲をそそる、色鮮やかな料理達。勿論、その横には少し怒った様子の母がいる。
珍しく寝坊をしてしまったけれど、今日は休日であるから問題はない。テレビの天気予報では、今日は1日晴れだった。
朝食を味わってから、外へ出る支度をする。寝坊した割に目覚めの良い私を物珍しそうに父が見ていたが、笑って誤摩化した。自分でも理由は分からないのだから仕方ない。
家を出る前にふと立ち止まる。悪い夢を見た時は、誰かに話すと良いとよく言うけれど、あれは本当だろうか。しばらく考えて、止めた。私には、あれが悪い夢であるとは思えなかったし、思いたくなかったのだ。何より、あの夢を自分だけの秘密にしたいと、そう思っている自分がいた。
天気予報の通り空は快晴で、ゆっくりと動く白い雲が、時の経過を教える。見慣れた街並であるはずなのに、全てが新しく感じた。行き交う人々も、話す言葉も、おそらく変わらないはずであるのに。はじめて、見たような。
ふと、いつもは視界の端で佇んでいるだけのカードショップの前で、立ち止まる。全く興味もなかったはずのその場所に、引き寄せられているようなそんな気さえした。
突然、肩を叩かれ振り返る。目に痛いほどの、クリスマスカラーが視界を覆った。
「名前、教えてくれるよな?」
ああ、彼が、「私」に笑いかけている。こんなに幸せなことはない。
ブルーの森で
back